|
|
話を聞かない男、地図が読めない女 (Why men don't listen & women can't read maps)
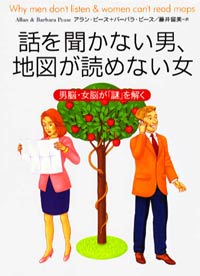 『話を聞かない男、地図が読めない女』
『話を聞かない男、地図が読めない女』
(Why men don't listen & women can't read maps)
著者 アラン & バーバラ・ピーズ (Allan & Barbara Paese)
訳者 藤井留美
主婦の友社
男と女は違う。 こんな明白な事実をだれも言ってなかったことに、まず驚く。 そしてタプーに挑戦しベストセラーにしてしまったピーズ夫妻に感謝。
タブーとは ・・・ 人種や性別、年齢などで人間を差別しない、技能や適正、能力において、男女差はない。 こうした「政治的に正しい」とされている常識に敢えて異を唱えること。
ピーズ夫妻はその前提が完全に誤りであることを、人類の進化を踏まえた調査・研究から導き出している。
男と女はちがう。 どちらが優れている、劣っているということではなく、ただちがう。 両者に共通しているのは、種が同じということだけ。 住んでいる世界も違えば、価値観もルールも違う ・・・ こうした書き出しで第一章が始まる。
この違いは何処から来るのか。 脳の構造・脳細胞のネットワーク構成がまるで違うことが原因のようだ。 外形 (頭蓋骨) や構成部品 (脳細胞) が同じであっても、配線や情報の処理方法が違えば、センサーや CPU・ソフトウエアが違うまったく別のシステムのようで、同じ環境に置いても、拾い上げる情報や導き出す結論が同じわけがない。 本書はそう言っている。
なぜ違ってしまったのか。 男は家族の糧を得るために狩を行う。 獲物を求めて野山を徘徊し、獲得した糧を携えて家族の元に無事帰らねばならない。 そのための肉体と地形を読む能力は生存の条件であった。
一方、女は子供を産み守るため、外部や家族の些細な状況変化も敏感に察知する必要があったし、コミュニティでの協調協力関係も不可欠であった。
こうした役割分担は種の存族に都合がよく、男女はそれぞれの役割に適合した進化を遂げた。 すべて必要に迫られた結果だ。 人類はこんな生活を 100 万年も営々と続けてきたのである。 当然先祖の学習は遺伝情報として我々に引き継がれ、結果として男女の脳はまったく別のシステムとして機能するようになった。 そんな話を実例らしきものを挙げながら説いてくれる。
と言ってもこれは学術書ではない。 書き方は実にやさしく、「うんうん」とうなづくこと請け合いである。 そしてこの脳の違いは、胎児期に形成されるというから目からウロコである。
「まったく男って・・・」、「女ってやつは・・・」といきり立っているあなた、本書を読んで異性の (もちろん自身も含めて) 思考システムを学び、理解することによって今より楽しい関係を築こうではないか。 それがピーズ夫妻の願いでもある。
- 男は冷蔵庫や食器棚に入っているものを見つけられない。
- 男の頭は問題点に索引をつけて整理できるが、
女の頭はひたすら問題をかきまわすだけ。 - 男は一度にひとつのことしかできない。
- どうしてモーゼは 40 年も荒野をさまよいつづけたのか?
人に道を聞かなかったから。 - 人間関係に悩みがある女は仕事に集中できない。
仕事に行きづまっている男は人間関係にまで気がまわらない。 - 男は女への愛の証しとして、世界一高い山にのぼり、世界一深い海にもぐり、世界一広い砂漠を横断した。 だが女は男を捨てた。
男がちっとも家にいなかったから。 - 男はアドバイスが大嫌い。 そのくせ解決策を出したがる。
- 男にとって失敗とは、敗北にほかならない。
- 女が悩みについて話すのは、ストレス軽減策にすぎない。
聞いてもらいたいだけで、解消して欲しいとは思っていないのだ。 - 男は問題を解決するために、ひとり石に腰掛ける。
- PMS (月経前症候群) の女とテロリストの違いは?
テロリストなら話せばわかってくれる。
そして極めつけのエピソードを一つ・・・
彼は持っている知識を総動員して問題点を見つけようとする。 そして解決策まで考える。
- I N D E X
- eの らぼらとり Home
- 表紙の一覧表示
- Book Title List
- 量子力学の奇妙なところが思ったほど奇妙でないわけ
- リザベーション・ブルース
- 利己的な遺伝子
- ユダヤ人の歴史
- 憂国のスパイ
- 森の生活
- 魔法の時間(とき)
- マネーロンダリング
- 報道は欠陥商品と疑え
- ビル・ゲイツ
- パラレルワールド
- 話を聞かない男、地図が読めない女
- 博士の愛した数式
- NEXT
- なめくじ艦隊
- なぜ数学が「得意な人」と「苦手な人」がいるのか
- 貞三先生の花言葉
- 恥辱
- ダ・ヴィンチ・コード
- 『脱アメリカ』が日本を復活させる
- 闘うプログラマー
- ソロス 世界経済を動かす謎の投機家
- 創世の守護神
- 戦争中毒
- 数学的にありえない
- 真珠湾の真実 ルーズベルト欺瞞の日々
- 国家なる幻影
- クライム・ウェイブ
- 空想科学読本
- 木を見る西洋人 森を見る東洋人
- 恐怖の総和
- 奇想、宇宙をゆく
- 神々の指紋
- オリバー・ストーン
- ウルカヌスの群像
ブッシュ政権とイラク戦争 - 裏切りの同盟
- 暗黒のシステムインテグレーション
- アメリカン・タブロイド
- アメリカの経済支配者たち
- アメリカの巨大軍需産業
- アホでマヌケなアメリカ白人
- 悪魔の選択
- アインシュタインのおもちゃ
- JFK謀殺・医師たちの沈黙
- JFK-ケネディ暗殺犯を追え-
- JFK暗殺 40年目の衝撃の証言
- JET STREAM
- 3001年終局への旅
- 2010年宇宙の旅
- 2001年宇宙の旅