|
|
木を見る西洋人 森を見る東洋人 (The Geography of Thought)
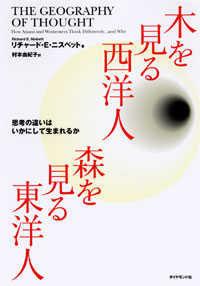 『木を見る西洋人 森を見る東洋人』
『木を見る西洋人 森を見る東洋人』
(The Geography of Thought)
著者 リチャード・E・ニスベット (Richard E.Nisbett)
訳者 村本由紀子
ダイヤモンド社
通常我々は、日常的な話をするにも冗談を言うにも重要な交渉を行うにあたっても、対象となっている事象について当事者同士が共通の認識を持っていると暗黙のうちに合意している。
対象について相手方が知らない場合は、それらの背景を説明すれば共通の認識を持ち得ると思っている。
共通の認識を持たない状況では、冗談は冗談にならず会議や交渉はまったく機能しなくなってしまうからだ。
それほど重要な共通認識だが、はたして人々は共通の認識を持っているのだろうか。
先に読み進む前に下の 2 つの設問を考えて頂きたい。 あなたの認識はどうだろう。
設問 1
次のうち、どの 2 つがより近いと思いますか。
A.パンダ B.サル C.バナナ
設問 2
ここに「ニワトリ」と「草」があります。
「牛」はどちらの仲間だと思いますか。 またその理由は何ですか。
一般的に人々は文化や宗教が違っても物事を知覚するプロセスは万国共通で、見聞きしたことの認知・認識は誰でも同じであり、同じ状況・証拠を提示されれば同じ結論に至ると思っている。
同じ絵を見れば同じものが見え、同じ状況に置かれれば同じ心理状態に至る。 こうした考えは多くの心理学者や社会学者たちも支持しており、いわば常識・定説となっている。
だがそれは真実だろうか。 もし、こうした認識が違っているとしたら、我々は実に甚だしい誤解をしていることになるのではないか。
リチャードが率いた研究チームはこの常識・定説に挑んだ。 多数の実験・調査によって得た膨大なデータを積み上げて仮説を打ちたて、さらに検証を重ねていった。
著者は認知・認識のプロセスの違いを際立たせるために、ギリシャの文化・思想を源流とする西洋人 (アメリカ・カナダ) と、中国の文化・思想を源流とする東洋人 (中国・韓国・日本) をサンプリングした。
結論は衝撃的である。 東洋人と西洋人では同じものを見てもその知覚・認知のプロセスが違うのだ。 端的に言えば違った世界を見ていることになる。
| さて、設問に対する考察。 |
|||||||||
| ≪東洋人的認識の選択≫ | ≪西洋人的認識の選択≫ | ||||||||
| 『設問 1』 | サル と バナナ が近い | パンダ と サル が近い | |||||||
| 『設問 2』 | 牛 と 草 が仲間 | 牛 と ニワトリ が仲間 | |||||||
|
|||||||||
人は世界の本質について基本的にどう考え、どこに注意を向けるのか。 関係を知覚するスキル、もしくは対象物を複雑な環境から切り離して認識するスキルをどの程度もっているのだろうか。 また、どのような原因推測を行い、世界をカテゴリーと関係のいずれで体系化するのだろうか。
古代ギリシャ人は分析的でカテゴリーを好み、世界を比較的単純であると捉え、対象物の固定的な属性や性質によって理解していた。 一方で古代中国人はカテゴリーに関心がなく、世界を複雑系の連鎖として捉え、対象物とその周囲の様々な力の場との相互作用によって理解していた。
こうした世界の捉え方の違いは、それぞれの社会の共通概念・国民性の違いを生む。 東洋人の関心は集団目標や協調的な行動に向けられることが多く、調和的な社会関係を維持することが個人の成功よりも優先される傾向があり、アメリカ人やカナダ人は他者との違いを過度に強調し、自分のことを実際以上に個性的だと考え、環境や持ち物に対しても個性的であることを好む傾向がある。
世界を単純であると捉えて分析的にアプローチするか、複雑であると捉えて調和的なアプローチをとるのか。 アプローチの仕方によって認知や推論は変わるし、その後の行動にも違いが現れる。
対立する命題に直面した場合、西洋人は矛盾を避けるために一方の命題を選んで他方を棄却するだろうし、東洋人は「中庸」を求めて両方の命題に幾ばくかの真実を見出そうとするだろう。 実際、西洋人は一方の命題を選択し、東洋人は中庸を是とするのである。
例えば意見や見解の違いが生じたとき、西洋人なら自分の意見の正当性を主張して相手の説得を始めるだろうが、東洋人は双方で歩み寄れる妥協点を模索し始める。
また、物事の結果や結論が自分の予想を裏切った場合、西洋人は自分の推論の正当性・合理性を主張して「そんな結果はあり得ない」ことをアピールするが、東洋人は「そうなることは分かっていた」、「そういうこともあり得る」と考える傾向がある。 西洋人が「過剰に論理的」であると批判され、東洋人が「曖昧・後知恵」と批判される所以である。
著者の研究チームでは、西洋人と東洋人の間では認知・認識のプロセスに大きな隔たりがあることを明らかにするとともに、そうした違いを育む要因が思想、文化、教育、社会から受ける (幼児期を含む) 影響、言語構造等々多岐に亘っていることも明らかにしている。
改めて身の回りを眺めてみれば、こうした認知・認識の違いによる彼我の文化の違いは、日常生活や日々のニュースの至る所で見られるような気がする。
それは飲み物の選択から意見の交換、嗜好品へのこだわりや政治・信条の表明、責任の在り方、はては国際紛争やその調停に至るまで枚挙に暇がない。
それならば東洋と西洋は、互いの認識の違いから決して理解しあうことはなく、永遠に諍いが絶えないのだろうか。
異なった社会的実践を経験したり、異なった社会的志向性を一時的にでも意識したりすることによって、ものの見方や考え方にも変化が生じることが幾多の研究・実験によってわかっている。 著者はここに一脈の希望をつなぎ、最後にこう結んでいる。
「洋の東西が交じり合うことで生まれるかもしれない新しい世界は、両方の社会や認知の特徴が生かされているものの、いずれも以前のままではない。 あらゆる文化の一番美味しいところが入った社会を望むのは、あながち無理なことではないかもしれない」。
恐らく誰もが「洋の東西では考え方に違いがある」と感づいているに違いない。 しかし「同じものを見れば同じように見えるはずだ」とも思っていたのも事実だろう。 リチャードはそうした曖昧で間違っていた、世界の「認知に対する認識」にハッキリと「NO」を提示したのである。
まさに「眼からウロコ」の一冊。 政治や外交・国際交流に携わっている方々には真っ先に読んでいただきたいし、市井にある者にも必読の書と言えるだろう。
- I N D E X
- eの らぼらとり Home
- 表紙の一覧表示
- Book Title List
- 量子力学の奇妙なところが思ったほど奇妙でないわけ
- リザベーション・ブルース
- 利己的な遺伝子
- ユダヤ人の歴史
- 憂国のスパイ
- 森の生活
- 魔法の時間(とき)
- マネーロンダリング
- 報道は欠陥商品と疑え
- ビル・ゲイツ
- パラレルワールド
- 話を聞かない男、地図が読めない女
- 博士の愛した数式
- NEXT
- なめくじ艦隊
- なぜ数学が「得意な人」と「苦手な人」がいるのか
- 貞三先生の花言葉
- 恥辱
- ダ・ヴィンチ・コード
- 『脱アメリカ』が日本を復活させる
- 闘うプログラマー
- ソロス 世界経済を動かす謎の投機家
- 創世の守護神
- 戦争中毒
- 数学的にありえない
- 真珠湾の真実 ルーズベルト欺瞞の日々
- 国家なる幻影
- クライム・ウェイブ
- 空想科学読本
- 木を見る西洋人 森を見る東洋人
- 恐怖の総和
- 奇想、宇宙をゆく
- 神々の指紋
- オリバー・ストーン
- ウルカヌスの群像
ブッシュ政権とイラク戦争 - 裏切りの同盟
- 暗黒のシステムインテグレーション
- アメリカン・タブロイド
- アメリカの経済支配者たち
- アメリカの巨大軍需産業
- アホでマヌケなアメリカ白人
- 悪魔の選択
- アインシュタインのおもちゃ
- JFK謀殺・医師たちの沈黙
- JFK-ケネディ暗殺犯を追え-
- JFK暗殺 40年目の衝撃の証言
- JET STREAM
- 3001年終局への旅
- 2010年宇宙の旅
- 2001年宇宙の旅