|
|
奇想、宇宙をゆく (The Universe Next Door)
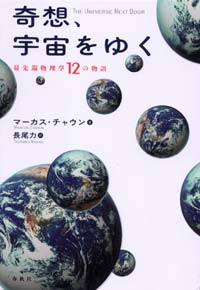 『奇想、宇宙をゆく』 (The Universe Next Door)
『奇想、宇宙をゆく』 (The Universe Next Door)
著者 マーカス・チャウン (Marcus Chown)
訳者 長尾力
春秋社
昔々、「ビッグバン」と呼ばれる、とてつもなく大きな爆発があった。 ビッグバン内部で生じた空間は劇的に拡大し、スープ状になっていた素粒子は時の経過に伴って徐々に冷えて原子・分子へと変貌を遂げる。 やがて生じた塵は互いに寄り集まって星や銀河を形成し、太陽系の第 3 惑星には生命が宿り始めた ・・・・。
このように理解していた宇宙の姿は、時々 TV の特集番組でも紹介されたりしていて定番の宇宙像という認識があった。
ところが・・・、 我々が住処としている宇宙の姿は、私たちが目の前にしている姿とは全く違う可能性があるらしいのだ。
自然界 (我々の住んでいる宇宙) の振る舞いは「物理学法則 (数式)」によって記述され、森羅万象は定められた方程式に従う。 放り上げたボールの行方や地球の軌道も太陽の活動も、この法則から逃れることはできない。
その方程式には四つの力 (基本力)(*1)が含まれ、それぞれには観測によって求められた「物理定数」もしくは「基礎定数」と呼ばれる値が定義されている。 基礎定数は古の昔から悠久の未来までその値は変化しない。
ここで単純な疑問が生じる。 基礎定数は何故その値なのか。 それより大きい値や少ない値では何故いけないのか・・・・。 逆説めいているが、この値でなければ人類 (知的生命体) は存在し得ないというのが事実なのだ。
人類 (その他あらゆる生命) の揺りかごである宇宙は、何故現在のような姿 (基礎定数の値) をしているのか・・・。 人類がそこに存在しているためだとする「人間原理」(*2)という発想がある。
宇宙の基礎定数と初期条件の大半は、ある程度微調整されているというのは定説になっている。 基本力や素粒子の質量が、知的生命の誕生に適するように現在の値に微調整されているからこそ、我々が存在し現在の宇宙の姿を観測しているのだ。
ならば、この微調整は偶然なのだろうか。 それとも意識的なものなのだろうか。
この問題について考えられる解釈の一つは、「宇宙が至高の存在である神の手によって人類のためだけに生み出された」とするものだ。 しかしこうした解釈は現在ではあまり広く受入れられていない。 そしてもう一つの解釈は「宇宙には複数の宇宙が存在しており、その一つひとつには多種多様な基礎定数が見られる」というものだ。
後者の解釈に立てば我々の住んでいる宇宙は、多種多様な姿をした沢山の宇宙の中の一つということになる。
こうした「多宇宙」という概念・認識は、生命のかけらも存在し得ない過酷な環境の宇宙が膨大に存在することを示唆する。 無味乾燥な、膨大な数の無駄ともいえる宇宙の存在を忌み嫌う研究者もいるようだが、「多宇宙」の概念は多くの支持を得つつある。
それでもなお、「自然はなぜ、この一連の方程式だけに従っているのか?」との問いを発したくなる。 この素朴な疑問に対する答えは次のようになる。
「知的生命の養育に適する幾多の条件 (基礎定数) は、人類が進化するのに適したものに違いない。 我々の住む宇宙が無数にある宇宙の中から選び出されたことは、そうした条件に適合 (まさしく我々の宇宙の基礎定数に合致) していることを示している。 こうした条件に育まれた人類がその環境を観測すれば、自ずと現在目にしている基礎定数を得ることになるのは自明なのだ。 我々が住む宇宙 (万物の理論) は、我々の存在によって決定付けられている」。 どうやら、物理学を最終的に決定づけているのは、生物学らしいのだ ・・・・。
宇宙を巡る研究はまさに百花繚乱。 世界の研究所では、時間の方向性の問題や多世界解釈、宇宙の成り立ちや生命との関わりといった、多彩で最先端の研究が行われ審判の日をまっている。 マーカス・チャウンはこうした研究を行っている研究者を訪問し、 12 の話題を取り上げて紹介している。
一つの話題から次の話題へ移るにあたり「つなぎ」の文章が用意されているので、独立した 12 の話は「つなぎ」のお陰で一貫性が保たれ、全体でお話を構成している体裁ともなっている。 が、それぞれは独立した研究・話題なので、どこから読み始めても支障はない。 うまい構成だ。
巻末には「用語集」があって、主だった用語が易しい言葉でさらりと説明されている。 気になる言葉や不明な用語は是非参照して頂きたい。 「用語集」を一読するだけでも、かなりの事情通になれる。
時には夜空に瞬く星々を眺め、その向こう側 (あるいは直ぐ隣) にある別の宇宙や、生命の神秘に思いを馳せるのも悪くない。 せっかく知的生命体として存在しているのだから。
(*1)【基本力】
あらゆる現象を支えていると考えられている四つの力。 四つの力とは、重力、電磁気力、強い力 (核力)、弱い力 (核力) をいう。
四つの力はそれぞれが絶妙のバランスで、知的生命の進化に適した値に調整されている。 もし、これ等の値が現在のそれと異なっていたらどうなるか。
| 重力 | |
| 数パーセントでも弱ければ、星の物質を圧縮して核反応を引き起こすようなことにはならず、太陽光など生じなくなる。 逆に数パーセント強ければ恒星は通常よりはるかに早く燃え尽き、知的生命の進化に要する数十億年もの寿命は保てない。 | |
| 電磁気力 | |
| 正電荷と負電荷に分けられ、双方の量は完全に釣りあっている。 我々の体は、正電荷と負電荷の総量にわずか 0.00001 パーセントの違いがあっても、一瞬でずたずたに裂け、体の各部が電気的な力で宇宙空間に吹き飛ばされる。 | |
| 強い核力 | |
| 原子核同士を結合させる役目を果たしている。 この力が数パーセント強まれば、太陽は爆発してしまうだろうし、数パーセント弱まれば、生命には不可欠の重原子を作ることは出来ない。 | |
| 弱い核力 | |
| ニュートリノ (崩壊しかけている恒星の中心部で生み出される) が物質と相互作用する際の要になっている。 弱い核力がほんの僅か強まれば、ニュートリノは物質との相互作用が活発になり、結果としてその数は激減してしまう。 逆にほんの少し弱まれば、ニュートリノは恒星の物質との関わりを持たなくなり宇宙へと拡散してしまう。 生命に不可欠の重原子は恒星 (大質量星) という炉で生み出され、やがて恒星が超新星となって崩壊する際、ニュートリノによって宇宙空間へ放出される。 | |
(*2)【人間原理】
宇宙が現在見られるような姿をしているのは、もしそうでなければ、そもそも人間など存在しているはずもなく、そんな事実が問題になることもない。 宇宙が現在のような姿をしているのは、人類がそこに存在しているためなのだ。
- I N D E X
- eの らぼらとり Home
- 表紙の一覧表示
- Book Title List
- 量子力学の奇妙なところが思ったほど奇妙でないわけ
- リザベーション・ブルース
- 利己的な遺伝子
- ユダヤ人の歴史
- 憂国のスパイ
- 森の生活
- 魔法の時間(とき)
- マネーロンダリング
- 報道は欠陥商品と疑え
- ビル・ゲイツ
- パラレルワールド
- 話を聞かない男、地図が読めない女
- 博士の愛した数式
- NEXT
- なめくじ艦隊
- なぜ数学が「得意な人」と「苦手な人」がいるのか
- 貞三先生の花言葉
- 恥辱
- ダ・ヴィンチ・コード
- 『脱アメリカ』が日本を復活させる
- 闘うプログラマー
- ソロス 世界経済を動かす謎の投機家
- 創世の守護神
- 戦争中毒
- 数学的にありえない
- 真珠湾の真実 ルーズベルト欺瞞の日々
- 国家なる幻影
- クライム・ウェイブ
- 空想科学読本
- 木を見る西洋人 森を見る東洋人
- 恐怖の総和
- 奇想、宇宙をゆく
- 神々の指紋
- オリバー・ストーン
- ウルカヌスの群像
ブッシュ政権とイラク戦争 - 裏切りの同盟
- 暗黒のシステムインテグレーション
- アメリカン・タブロイド
- アメリカの経済支配者たち
- アメリカの巨大軍需産業
- アホでマヌケなアメリカ白人
- 悪魔の選択
- アインシュタインのおもちゃ
- JFK謀殺・医師たちの沈黙
- JFK-ケネディ暗殺犯を追え-
- JFK暗殺 40年目の衝撃の証言
- JET STREAM
- 3001年終局への旅
- 2010年宇宙の旅
- 2001年宇宙の旅