ストラディヴァリ
ジョルジ・サーントー著 / 田才益夫訳
ストラディヴァリ (全四楽章よりなる大長編小説)
翻訳者の序言または解説
*** 全編完結 ***
第一楽章 アレグロ・コン・ブリオ
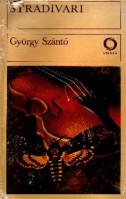
ラジオ。
天国の鉱泉から清らかな水が流れ出るように、バイオリン独奏の音がスピーカーから静かに流れてくる。そのバイオリンの音は私と同じように、ただひとり孤独に無限を探索している。その音はおのれの孤独なる愉悦によって満たされ、また孤独によって完璧となる。それは暗い地下室の黴のはえた丸天井の下の蜘蛛の糸の網におおわれ、錆びた鉄のたがのはまった樽の底の古いワインに似ている。
私のなかでも何かが清らかになる。
いつの頃からか私は骨の髄まで錆びついていた。だから、わたしは、あわてて空気のような、ふわふわした蜘蛛の巣を私の心からぬぐい去ったのだ。
かつて、私は深淵から上方へ、そして空高くはばたくバイオリンの音楽と同じく、人を酔わす古いワインのような孤独に酔っていた。私の体の各部分は音楽に共鳴して鳴りはじめ、私自身の生命が音楽のなかに流れ込む。
私は後悔している年老いた罪人だ。
私はかつてピアノ、オルガン、大オーケストラのポリフォニーのみを愛していた。
いま、私はバイオリンの孤独のなかで後悔している。同様に、古い楽器の形のなかのすばらしさを痛感し、その形のなかにすべてを見いだしている。線、色、それに彫り。はたして、バイオリンの完結した形態のなかにあるよりも、完璧な線を創造できるグラフィック・デザイナーがいるだろうか?
また、もしかして、バイオリンのもつ暗い火の色のスケールをその陰りと輝きの陰影のなかでとらえ、いまにも消えるかと思えば、めらめらと燃え上がる炎の青白い黄色から濃いい茶色にいたるまで、また赤錆色にはじまり黒におわるまでの色の音階を、たとえ夢想のなかとはいえ思い浮かべることのできる画家がいるだろうか?
均整やふくらみ、傾斜と f 字孔の切り込み、これらの形のなかにおぼろげに感じられる繊細さにとことんほれ込むことのできる彫刻家がいるだろうか?
これらすべてのものたちは、音の生れるところで立ち止まる。
しかし、バイオリンの均整のとれた形の美しさは、まさに音を生み出すことによって、はじめて意味をもつ。そのためにうまれ、成熟し、みばきあげられ、完成されたのだ。その永遠の持続のために、その音のために……。
私はバイオリンを聞いている。その音はラジオのスピーカーを通って私のところへたどりつく。
バイオリンの魂からラジオの魂は通じる経路をたどってみよう。すると、そのあいだには山があり、山の斜面や花咲く川の岸辺がある。また、何世紀もの激流のなかを――そこに光があたってきらきらと反射する――秋の紅葉の茂みの下を、民族の運命的影のなかを、苔むす岩陰を伝ってきたのだ。
市場の騒音、独自のスタイルをもった時間、時代の象徴。それらは相互に厳しく監視しあっている。ほら、カーニバルの行列。野っ原を後進する兵隊たち。それらはすべて無言の星空の下の閲兵だ。石造りの家並のあいだのアーチ型の通り抜けの通路にひそむ暗殺者たち。山の尾根のエーデルワイスの花も……。
ぼろをまとった放浪者がごみ捨て場で食い物をあさっている。そして、そこでは宝石で飾った雄鶏が支配している。草の茎のあいだでは色とりどりの羽をつけたカブトムシが、原生植物と何百万年という歳月の日陰のマンモスの代用として戦っている。
小さな皇太子が太陽王に変身する。
太陽の光の奔流のなかで、長い髪のかつらがまばゆく輝く。金色で縁取りされた真紅のフロック、黒いビロードないしは絹の三角帽、膝下までの紫色のズボンと留め金つきのやわらかな革靴のあいだの白い絹の靴下。黒皮のさやに入った真鍮の柄つきの短剣――これが私の学生時代の小さな田舎町の劇場の舞台で見たロココ時代の記憶である。
たぶん、コレルリも長い髪のかつら、そして、のちには後ろに束ねたかつらをかぶっていたはずだ。バイオリンの巨匠たちのことを記述した本のなかで、鼻の大きな悪人面をしたガエタノ・プニャーニを見たことがある。
サヴォイの皇太子オイゲンが鼻息も荒いスペイン産の黒馬にうちまたがって、ロンバルディア平原の洗浄を駆けている。キラキラ輝く胸鎧の面長の顔はすごく青白く、例のコルシカ出身の伍長のように馬をうまく操ることができない。地獄の舞台の上では、どこかの背の高い気の狂った男が演じている。
E・T・A・ホフマンもハイネも、このくしゃくしゃ頭のうしろで悪魔がバイオリンをごりごりとかき鳴らしているとたしかに言った。
その後パガニーニはパリへ出かける。そこで彼の周辺のコンサート・ホールの客はコレラで刈り取られる。さらに「ライプツィッヒ絵入り新聞」の写真の原板がある。
ポツダムの練兵場では親衛隊の隊列のまえを皇帝ウィルヘルム二世がその六人の子供たちとともに進んでいる。
それとコレルリの『ラ・フォリア』とどんな関係があるのだ?
ここにはたしかに、キラキラ輝くまでに磨き上げられた軍楽隊の騒々しさがある。そしてボヘミア風カフェを名のるライプツィッヒガp・ストラッセのバルトリーニの店、カフェ・デア・ヴェステンス。テーブルの上にはゲルハルト・ハウプトマンの禁欲主義者の顔がある。二人の顔中髭面の男。バールとズーダーマン。マルズスカー・エゼラ、パリ凱旋門のてっぺんの元帥杖、ベートーヴェン・ザールでの忘れることのできないシマノフスキーのバイオリン協奏曲――そして、次にはストラディヴァリを納めた釣鐘状のガラス・ケースの上のほうでサキソフォーンを持って微笑を浮かべた黒人がそびえている。
コレルリの『ラ・フォリア』の演奏がおわった。私は時間の蓄電器(コンデンサー)のダイヤルを少しまわす。ジャズ。それについての叙事詩(エポス)はほかの誰かが書いてくれるだろう。いまは私はバイオリンにかんするエポスを書かなければならない。そのエポスは私の心のなかに湧き出し、私の心のなかを流れ、私の心のなかで波打ち、私の心のすみずみまで満たす。
私は辞典を見る。プレシア、クレモナ、アマーティ、サロー、グァダニーニ、グァルネリ、そして――ストラディヴァリ――彼こそが主要人物であり、まごうかたなきバイオリン造りの王者である。
彼を間近に見てみよう。生れたのは1645年から1650年までのあいだのいつか、死んだのは1737年である。正当な市民権をもつ家庭、いちじるしい物質的豊かさ。子供とバイオリンにかんするかぎり驚くべき生産量である。彼は11人の子供と三千の楽器の父である。模範的な人生。バイオリン製作の名だたる職人組合の重鎮。
まさにそこにこそ落とし穴があるのだ。このように敬虔な大家族の父親が、いったいどんな叙事詩の主人公になれるというのだ? 彼についてどんなロマンが書けるというのだ? 私は競争と不幸と、冒険と不正、そして和解に満ちた生涯を期待していた。絶望と至福、深き淵よりの絶望の叫びと天国のベアトリーチェ、あますところなく、すべてを、彼が自分のバイオリンに吹き込んだものすべてを期待していたのだ。
ところがどうだ、いま、白い布の帽子をかぶって、白い革の前掛けをつけて、背の高い痩せぎすの、清潔な男が私の前に立っている。その姿は、彼の弟子の一人で、何年かののちに、その工房を彼とともに支えることになる男が記したのと同じだ。
私も知っている。それはおもしろくもおかしくもない、平均的人々だ。ドストエフスキーなら、ほかの作家たちが世界を支配する軍隊の指揮官の波乱に満ちた生涯から引き出すよりも多くのものを、これらの人々から引き出すことができるだろう。アル・カポネよりは街のごろつきのほうが、フォードよりも田舎の商人のほうが、ナポレオンよりはただの擲弾兵のほうが多くのもを与えることができる。
しかし私がバイオリンのなかに発見したもの、そしてバイオリンについて語りたいと思うことのためには、辞典にも専門書にも語られていない、ストラディヴァリのもう一つの生涯が必要になる。その生涯を私はかれとともに、あらためて、長い髪のかつらからサキソフォンまで経験しなければならない。
このようにまえもって、この作品誕生の背景のすべてをあからさまにして、理解しておいてもらい、工房の匂いをほんのちょっとでも嗅いでもらうのは、あながち悪い戦略とはいえまい。たしかに私は神とストラディヴァリの仕事場のドアを開けたいと思っている。しかし、構成、性格、様式を誰もそんなに言葉どおりには取らないだろう。
このような場合に、そのほかにも何かわけのわからないものが想定される。誰も叙事詩に大きな流れや客観性を期待しないし、人間の魂の地下道や崖の小道の幻想的なからみあいなど予想もしていまい。みんなは無限を観望する孤独な声、いくつかの幻覚、少しの涙、あきらめからもれ出す微笑のようなものだけが、来るだろうことを知っている――そして、それですべてだ。
たとえば、いま、クレモナのトラッツォ鐘楼の鐘の音が聞こえる。そこの私の前には、霧の中からそのおぼろげな形が浮かんでくる。四面の基盤に八角形をした接続部、短い庇のついた小さな窓――そのたくさんな庇の下の新しい巣のなかには、つばめの雛がピーピーと鳴いている。それらの声を鐘楼の鐘の響きが飲み込んでしまう。
それはやがてパレード用の軍服を着た軍楽隊の鋭い金属的な音となり、いま、ポツダムの練兵場で響きわたるのを私は聞いている。私は広い領域をさまよっている。しかし、最後には、私のなかでオーケストラのけたたましい大音響が勝利を占める。そして私はいよいよ、ウィルヘルム二世皇帝が六人の皇子とともに整列をした近衛兵の隊列の前を進んでいく場面を物語らざるをえなくなった。