
近頃、どうも駄菓子屋が暇暇暇・・・。
原因はなんとなく分かってる。探偵業をメインにしちゃってるからだ。
けれど他にも原因がありそう。そう、おそらく駄菓子屋の商品が良くないんだ!
昔ながらの・・・なんて売り文句じゃあいけない。
そりゃまあ、うちの店独自のってのはあるけど、やっぱりねえ・・・。
というわけで時間をもらって、うちの店に店長さん達に集まってもらったのでした。
なんで店長さん達か?それはまあ、普段からいろいろ見知っているから。
「・・・えー、かくかくしかじかという事で、店が繁盛するような商品を考え出してほしいのです。」
「やっぱりラーメンよねえ。もしくはカレーライスとか。日本人が求めるのはそういう料理。
という事で駄菓子屋もそれを真似てラーメンせんべいとか、カレー餅とか良いんじゃないかしらぁ。
そうだ、どうせだったらくじもつけちゃいましょう!当たった人は飴舐め放題!!
あっ、飴で何か作るのも良いわねえ。飴ラーメンなんてどうかしら?
ラーメンのどんぶりに麺の代わりにほそ~く延ばした飴を入れるの。
おおうけよ、絶対。ねえ、神無月さん。」
「それいいですね。さらに手品をつけましょう。一品に一ネタ。」
「なるほどぉ!!これで繁盛は間違い無しね!!まあ~、いきなり解決しちゃったわ!!
さあさ皆さん、おしゃべりしましょう。」
「あっ、その前にこの前あみ出した新技を・・・。」
「勝手に話を進めてんじゃなーい!!!」
ぜえ、ぜえ・・・。まったくこの二人は・・・。
あたしはスピーカー片手に大声で怒鳴りつけた。
その直後霜月さんが、如月さんと神無月さんの首根っこをひょいっと持ち上げた。
「悪いけどあんたらは帰ってくれ。ややこしくなるだけだ・・・。」
「ええー?なんでですかぁ?」
「あの、せめて一技披露させてくれませんか?」
「はいはい、それはまた今度。じゃあな。」
ぽいっ、とふたりを外へ放り出した霜月さん(ゴミじゃないんだから・・・。)
がらがらがら・・・ぴしゃん!
と、扉を閉じて、自分の居た席に座り直した。
「たくう、誰だね。あの二人を連れてきたのは。」
「師走、あんただろうが。そのくせ睦月と極月が居ないなんてどういう事だよ。」
「あ、いや、その、あはははは・・・。」
卯月さんと霜月さんに睨まれて笑ってごまかした後にうつむく師走さん。
そう、今回の召集はあたしが師走さんに頼んだものだった。
日頃しょっちゅう依頼をしに来るんだからこれくらいは働いてもらわないと。
けどそれが良くなかった。霜月さんが言うとおり、
こういう話に一番頼りに成りそうな睦月さんと極月さんが居ない。
二人とも何らかの用事で急ぎ気味だったようなので、詳しい理由は告げなかったとか。
はあーあ、こんな事なら葉月さんに頼むべきだったかなあ・・・。
で、うなだれていると、その葉月さん(アシスタントの役)が横から突ついてきた。
「智子ちゃん、がっくり来てないで続き続き。」
「え?あ、うん。それで、最初に言ったように新製品を提案してください。
とりあえず出来る物を採用していって、売れ行きが良かったらあたしが何かプレゼントします。」
「質問ですう!」
まん前に座っていた霧塚さんが手を挙げた。
「はい、なんですか?」
「種類とかはこだわらなくてよいのですか?いくらなんでもラーメンは・・・。」
「あ、そうですね。ええと、とりあえず和菓子でいこうかと思います。」
「それなら俺も質問!」
今度は右の方に座っていた水無月さんが手を挙げた。
「はい、なんですか?」
「別に和菓子にこだわらなくても洋菓子とかも混ぜちゃあどうだい?ケーキとかさ。」
「あの、うちは駄菓子屋なんですけど・・・。」
「かあー、細かい事気にするねえ。まあ、文月さんがそう言うならしょうがないやな。」
別に不満そうでも無く納得して頷く水無月さん。
さすがに洋菓子はねえ・・・。だいたいそれなら霧塚さん所でも売られてるし。
「他に質問はありませんか?」
「は~い、質問です~。」
手を挙げたのは奥のほうに座っていた皐月さん。
「はい、なんですか?」
「和菓子といっても具体的に何ですか~?」
ほっ、まともな質問だ。
「え~と、せんべいとか飴とか・・・。って、とにかく駄菓子ですよ。」
「でもさんこちゃん、駄菓子っていろいろあるじゃない?
それこそ考えてたらきりが無いんじゃない~?」
さんこ・・・。気にしない気にしない・・・。
「だから、全部じゃなくっても思いついた物でいいんですって。
そんなに深く考えなくって良いですよ。」
「そうなの~、分かったわ~。じゃあフルーツ飴なんてどうかしら~?」
いきなり提案する皐月さん。周りは一瞬ざわついたものの、よく考えて静まった。
その中から代表するように菊月さんが申し出た。
「皐月さん、それは普通にありますよ。もっと珍しい物じゃないと。」
「ええ~?そうなの~?うーん・・・あっ、そういえばきくぬきさん家って薬屋さんなのねえ?」
最初は分からない顔をしていた菊月さんだったけど、しばらくして頷いた。
「そうですけど、それが何か?」
「毒薬とかもあるのよねえ?」
「はあ?」
毒薬ぅ?何を企んでるんだろ、皐月さん。
ここで再び周りがざわざわと・・・。
「そりゃまあ、作れない事も無いですけど・・・一体何に?」
「りんごに入れて毒りんご!!これで完璧よ~。」
聞いた途端硬直する菊月さん。そこへ水無月さんが入っていった。
「おい皐月さんよお、りんごは駄菓子じゃないぞ。」
「あっ、そうかあ!!うーん、それは盲点だったわね~。
ありがとう、みかづきさん。」
「いやいや、はっはっは。」
照れて笑っている水無月さん。
あのねえ、りんごとかの前に毒ってことに問題があるでしょうが。
はあ、何でこんな人達がこの重要会議に参加してるんだろ・・・。
「智子ちゃん、気を取り直して話進めよう。」
ショックを受けてる所へ葉月さんがちょいちょいと慰めてくれた。
そ、そうだよね。こんな所でへこたれていられないよね。
「それでは、今から皆さんのアイデアをまとめて行きたいと思います。
皆さん、積極的に意見を出していってください!!」
とりあえずあたしが期待してるのは卯月さんと霜月さんと菊月さん、そして葉月さんと霧塚さん。
この五人は普段から真面目だからね。よく考えたら後の人いらなかったんじゃ・・・。
と頭の中をめぐらせているとすっと手を挙げた人物が。
「・・・・・・。」
あっ、長月さんを忘れてた。そうか、この人こそ頼りにしていいかもね。
「はいどうぞ、長月さん。」
「・・・飲み物、持ってくる。」
それだけ言うと静かに立ちあがってその場から出ていった。
・・・やっぱり頼りにするべきじゃないかも。
「長月って気が利くよなあ・・・あれ?なんでここへ来る時に持ってこなかったんだ?」
「どうせしらすさんが忘れてたんじゃないんですか~?あたし達を連れて行く時だって随分あせってたし。」
「うっ、面目無い・・・。それより俺は師走なんだけど・・・。」
「え?しわとりさん?」
「いや、しらすでいい・・・。」
たくう、そういう事か。まったく師走さんは・・・。
それにしても皐月さんの相手をまともにしちゃあ駄目だっての。
「はい!」
元気よく手を挙げてくれたのは霧塚さん。よっし、本命だ!
「どうぞ、霧塚さん。」
「レインボージュースとかはどうでしょうか?名前の通り七色に光るんですよ。」
「それは凄い!・・・って、どうやって作るればいいんですか?」
「それぞれの色を持つ無害な食べ物を利用しては・・・そうだ、飴の方が良いですわね。」
「なるほど、七色に光る飴ですね。」
笑顔で頷いて早速葉月さんに書いてもらう。作るのは大変そうだけど、アイデアとしては良いかも。
光るってのは難しいかな・・・。でも、飴はうちの専門中の専門!!
せっかく案が出たんだから是非作ってみないとね。
「さて、他にはないですか?」
「はい。」
「どうぞ、菊月さん。」
「食べると何らかの活力が出るようにしてはいかがでしょうか?
ビタミン、ミネラル等の栄養が補給できるとか。」
活力?栄養補給?それって健康食品になっちゃうんじゃ・・・。
「菊月君、私達は駄菓子を作るんだ。そんな裏でこってても仕方ないだろう。」
「しかし卯月さん、近頃の若者の栄養不足は深刻ですよ。」
「だからって駄菓子を薬代わりにするのは感心しないな。だいたい、どうやって売るんだい。」
「出来たお菓子に注入すればいい事ですよ。私はそういう道具を持っています。」
なるほどね、後で注入・・・待てよ。
「菊月さん、作るのは良いんですが見た目は変わらないですよね。どうやって知らせるんですか?」
「そうか、事前に言ったんじゃあ余計買わないかもしれませんね。
こうなったら隠して・・・駄目だ駄目だ。成分を隠して売るなんて犯罪ですね。
すいません、私の意見は聞かなかった事にしてください。」
難しく考え込んだと思ったら、菊月さんは残念そうにうつむいてしまった。
結構いい案だと思うんだけど、やっぱりそれだと駄菓子らしく無くなっちゃうしね。
さてさて、まだ二つ。こんなんじゃあ当然終われるわけが無い。
他に意見は無いかなあ、とみんなを見まわしていると・・・。
「はい。」
「どうぞ、霜月さん。」
「でっかい物を作ったらどうだ?」
「でっかい物?」
豪快な霜月さんらしい意見。けれどでっかい物ってどういう事だろう。
「置いてあるお菓子、それぞれの大きいバージョンを作るんだよ。
スーパーとかに置いてあるお菓子の中にも大きくしたのがあっただろう?
それと同じように、飴とかも大きくして売るんだよ。」
「大きく・・・って、どれくらいですか?」
「そうだな、一メートル・・・は無理だろうから三十センチくらい。」
「それくらいなら出来そう。なるほど、大きくかあ・・・。」
感心して葉月さんにそれを書くように促そうとする、という前に師走さんが意見を発した。
「あのさあ、作ったところで誰が食べるんだい?いくらなんでもそんな大きいのは・・・。」
そこであたしははたと止まった。たしかに、直系三十センチの飴なんて誰も食べないだろうな・・・。
「師走、何てこと言うんだ。人間やってやれない事は無いぞ。」
「霜月、あんたなら食えるかもしれないが他の連中は食えないと思うぞ。」
「なんだって?じゃあ決をとろう。俺の提案した菓子が食えるって奴、手を挙げてくれ!」
勝手に事を進めちゃってるけど・・・。
纏め役はあたしなんだからあんまりそういう事はしないで欲しいな。
それで、手を挙げた人は・・・霜月さんただ一人だった。
「・・・そんな馬鹿な。ちっ、あきらめるか。」
がっくりとうなだれた霜月さんを見て、やれやれと顔を見合わせるあたしと葉月さん。
とその時、ガラッと扉が開いたかと思うとたくさんの飲み物を持ってきた長月さんが。
「お帰りなさい、長月さん・・・。」
「長月さん、それはちょっと沢山持ってきすぎたんじゃないんですか?」
なんと、ビールケースくらいはあろうかという大きさの箱にたっぷりジュースの缶を入れている。
・・・と思ったら、これってクーラーボックスだ。こんな物にわざわざ入れてきたんだ。
「気が利くわね~、ながいすさんって。ちゃんと冷えたのをもってきたんだ。」
言うなり一番にジュースを手に取る皐月さん。
丁度いいや、少し休憩にしようっと。
「皆さん、しばらく休憩を取ります。
長月さんが持ってきてくださったジュースを飲みながらゆっくりと。」
パンパンと手を叩いて机の前にぺたんとうつぶせる。
はあ、なんだか疲れちゃったなあ。この調子で大丈夫なのかな・・・。
しばらくそのままでいろいろと考え事をしていると、首筋にひやあっとしたものが!
「うわあっ!」
慌てて体を起こすと、そこにはジュースの缶を持ってにこにこしている霧塚さんが。
「智子ちゃん、考えすぎは良くないですわよ。
さあさ、長月さんが持ってきてくださったジュースを飲んで。」
「は、はあ、どうも。」
いきなりの事にびっくりしたけど、あたしの事を心配して・・・。
なんだかありがたいなあ。って、よくよく考えたら無理を言って集まってもらってるんだった。
あたしがこんな所で落ちこんでちゃあ・・・。
「どうしたんですか?智子ちゃん。」
「なんでもないです、ありがとうございました。」
ごくごくごくとジュースを飲み・・・
「ぶーっ!!こ、これって・・・。」
「ちゅーはいですわ。」
「ちゅ、ちゅーはいぃ!?」
「ええ、この程度だったらジュースと同じでしょう?」
「ジュースじゃないですよ、チューハイは!!!」
慌てて缶をテーブルの上に置く・・・と、他のみんなが飲んでいるのは普通のジュースみたい。
なんであたしだけチューハイなんて手渡されちゃったの?
「智子ちゃん、チューハイお嫌いなんですか?」
「だああ、あたしは未成年なんですってば!!」
「でも・・・。」
「霧塚さん、その辺でおいときなって。ほら智子ちゃん、こっちは普通のジュースだから。」
「あ、おばさんありがとう。」
それなりに反論してくる霧塚さんを押しとどめて葉月さんがジュースを手渡してくれた。
うん、今度は本当に普通のジュースだ。安心して飲もうっと。
ごくごくごくと今度こそジュースを飲み・・・
「ぶーっ!!こ、これジュースじゃないよ!!」
「あらそう?おっかしいわねえ・・・あ、ラベルが貼られてあるんだ。」
「へっ?」
ぽかんとしていると、葉月さんはあたしの手から缶を奪い取ってべりべりとそれをはがす。
と、中から現れたのは、なんとまたもやチューハイ・・・。
「なんでこんなもんが・・・。」
「ごめんね、智子ちゃん。ちょっとー、長月さん!!
駄目じゃないの、こんなお酒なんて持ってきちゃあ!!」
「・・・面目無い。」
遠くからぺこりと頭を下げる長月さん。
まったく、しっかりして欲しいなあ。なんであたしがお酒なんか・・・。
少し不機嫌そうにすねていると、師走さんが新たなジュースを持ってきた。
「不幸だったねえ、智子ちゃん。ほら、今度こそ普通のジュースだ。」
「本当にそうですか?」
「ああ、本当だとも。」
「まあ今度は大丈夫そうですね。」
ラベルを大袈裟に貼っている様でもないし、なによりお酒の匂いがしない。
というわけで安心してそれを飲もうとしたんだけど・・・。
「でも智子ちゃん、二度あることは三度あると言いますわ。」
という霧塚さんの声にぴたっと止まった。
そうだよねえ、これがもし師走さんが仕組んだ物だったら・・・。
じとーっと師走さんを睨んでいると、慌てて手を振ってきた。
「おいおい、心配しなくても大丈夫だって。
・・・そうだ、二度あることは三度ある菓子とかはどうだい?」
いきなり新製品の提案をしてくるとは・・・。
というわけで、葉月さんと霧塚さんと一緒になって注目した。
「なんですか?それ。」
「つまりだ、一個買って当たりを引く。で、また当たったら更に当たりがもらえるってすんぽうだ。」
「・・・意味がよくわかんないんですけど。」
「だから、二回連続で当たったならば無償で三回目を当たりにしようって事だよ。」
「・・・それって、新製品なんですか?」
「いや、当たりにつられて買いにこようって人が増えるかもよ。」
「・・・考えておきます。おばさん、一応メモっといて。」
「はいはい。」
三度目も当たりねえ・・・。
それ以前にうちに当たりつきのお菓子なんてあったのかなあ。
まあいいや、保留って事で置いておこうっと。
「智子ちゃん、もう一つ思いついた。謎付きのお菓子ってのはどうだい?」
「謎付き?」
「そうだ。とにかく何でも一つ買った時にクイズとか謎のようなものを出す。
で、その答えを知るためにはもう一つ買わなければならないってすんぽうだ。」
「師走さん、それって押し売りみたいですわ。」
傍で見ていただけの霧塚さんが口を開いた。
確かにそんな気がするよねえ。師走さんの言うそれは、いわばおまけで引っ掛けて、ってことだから。
押し売りって訳じゃないかもしれないけど、やっぱり・・・。
「霧塚さん、押し売りなんて非道いよ。
俺はあくまでも買いたい人が買うようにって事を考えたんだから。」
「でも、クイズの為にお菓子を買わなければならないなんて・・・。
そのうち噂になるんじゃないですか?あの店はクイズを盾に商売してるって。」
「・・・なるほど。それじゃあ俺の案は却下だな。」
霧塚さんが言う事はなんだか大袈裟って気もするけど、そうならないとは言い切れない。
現に手品に夢中になってる人とかいるんだし、クイズ狂とかいう人が現れてもおかしくない。
そんな人が集中してお菓子を買っていったら・・・。
「はあ、なかなか難しいなあ・・・。」
うなだれながら、思っている事をついつい口に出す。
すると、慰めるように葉月さんがあたしの肩を叩いた。
「まあまあ、三人よれば文殊の知恵とか言うし。これだけ人がいれば必ず何かいい案が出るよ。」
「そ、そうだよね。すでに霧塚さんのが一つでてるし。」
気を取り直すべく四人で顔を見合わせて頷く。そしてあたしは元気よく立ち上がった。
「では再開します。何でも意見を言って下さい。」
先ほどまで皆いろいろ相談してくれていたのか、すっと手が挙がった。
「え~と、まず卯月さん。」
「どうも。ともかくおまけのようなものは必要じゃないかと思う。
くじにしたって、師走が言ったクイズにしたって・・・。」
結構離れてたのに聞こえてたんだ。密かにちゃっかりしてるなあ。
「それで、他には無いようなおまけを考えてはどうだろうか?
例えばそう・・・おもちゃとか。」
「どんなおもちゃですか?」
「きせ・・・待てよ、やっぱり止めだ止め。おまけに金がかかってしまっては元も子もない。
智子ちゃん、すまないがこの事に関しては忘れてくれたまえ。」
「は、はあ・・・。」
きせ?一体何を言おうとしたんだろう・・・。
あきらめたように首を振った卯月さん。次の意見を求めようとしたとき、水無月さんが立ちあがった。
「待った待った、おまけなら俺の所で考えてみるって。イカした物を作るのは得意だからさ。」
「しかし・・・。」
「水無月さん、イカした物ってどんな物ですか?」
難しい顔をしている卯月さんを遮って霧塚さんが質問する。
あんまり期待しない方がいいと思うんだけどな・・・。
「よくぞ聞いてくれた。ずばり、折り紙だ!俺はこう見えても手先は器用なんでな。」
得意げに手をひらひらと動かして見せる。
へえ、折り紙かあ。ふむふむ、それならいいかもしれない。
水無月さんの事だからいろんなもの知ってるだろうし・・・。
「でもみかづきさん、どこから折り紙を?
いくらなんでも全てにおまけとしてつけてたら大変な量でしょう?」
隣から皐月さんがそれなりに意見を言う。なんだ、結構ちゃんと話聞いてるじゃない。
普段からこうだと助かるんだけどなあ。
「それは大丈夫だ。文房具屋の店長、
つまり神無月さんに・・・って、その神無月さんはどこ行ったんだ?」
「さっき霜月が外へ捨てただろう。」
「なんだって!?ちくしょう、もうゴミ収集車が持っていったんじゃ・・・。」
「みかづきさん、生ゴミは今日じゃないですよ~。」
「そうか。それなら良かった。ひとっ走り行って・・・」
「まったまったまったー!!!」
慌ててあたしは大声で叫んだ。
冗談じゃない。なに勝手に訳のわかんない話を進めてるんだか。
霜月さんが捨てたってとこからがいけないんだよ。全く師走さんは・・・。
じろりと師走さんを睨んだ後に水無月さんへ向かって告げる。
「後で電話なり何なりすればいいじゃないですか。それより、まだこの件は片付いてませんよ。」
「なんだって?折り紙を請求すれば終りなんじゃないのか?」
「だって、どんなものを作るとか色々あるじゃないですか。」
力強く告げると、横から葉月さんが言ってきた。
「そういうのは後でじっくり相談すればいいの。ま、とりあえず神無月さんには電話でもしておくよ。」
「はあ・・・。え~と、それじゃあ水無月さん、お願いしてよろしいですか?」
「よろしいですか?全く遠慮気味だなあ。俺は積極的にやるから。
丁度暇つぶしになっていい事だし、張り切って折らせてもらうよ!」
水無月さんがガッツポーズを取った。葉月さんはその件に関してメモ。
とりあえずそこで、折り紙に関しては終りとなった。
駄菓子のおまけのために・・・なんだか申し訳無いなあ。
「さて、他に・・・どうぞ菊月さん。」
「どうも。えーと、やっぱり何らかの物を入れてみては・・・。」
それって最初の方に言っていた栄養関連のことかな。
「菊月、それに関しては止めにしたんじゃなかったのか?」
「いえいえ、健康を考えたとかじゃなくて、いろんな味が楽しめるとか・・・。」
いろんな味?
「菊月さん、それって私が考案したレインボー飴のような物ですか?」
霧塚さんが不思議そうに尋ねると、菊月さんは自信たっぷりに頷いた。
「そう、そんな感じです。一つのお菓子で二つ以上の味が楽しめるような。」
「で、それはどうやって作るんだい?」
と、葉月さん。確かにそうだよね、作るとなったら・・・。
「簡単ですよ。その味がするように素材を注入して。」
「・・・それって薬と同じように作るってことですか?」
「いやそうじゃなくて・・・。では、一度私が作って持ってきましょう。
となると早速試してみなくては・・・先に帰ってもよろしいでしょうか?」
いきなりいそいそと立ちあがる菊月さん。
気が早いその姿に、周りの人は唖然として見ていたけど・・・。
困ったような顔をしている葉月さんに横から突つかれたけど、あたしは一つ息をついて口を開いた。
「ええ、どうぞ。期待して待ってます。」
「そうですか。では私はこれにて失礼させていただきますね。」
軽くお辞儀をしたかと思ったら、ガラガラと扉を開けて菊月さんは帰って行った。
ま、やる気になっている人の出鼻をくじく事無いよね。
とにかくそれがすごい物なら言う事なし。例え失敗しててもそれを参考にしてまた何か出来るかも。
というわけで、あたしは今だざわついている皆を手を叩いて制した。
「はいはい、それでは他に意見は有りませんか?」
「・・・・・・。」
今度手を挙げたのは長月さん。けれど無言のまま手を挙げるのは止めて欲しいんだけど・・・。
「どうぞ、長月さん。」
「ああ・・・。」
一言返事をしたかと思ったら、何やらきちんと座り直したみたい。
几帳面なのかそれともただの癖なのか。どっちにしても無言ってのは・・・。
でも、しばらくそのまま・・・つまり無言のままってこと。
首を傾げながら他の皆と注目していたんだけど・・・。
「・・・やっぱりだめだ。」
長月さんは首を横に振ったかと思うと、あきらめたように手を振った。
しばし呆然・・・。
あのねえ、勝手に自分で納得して止めるなんてそりゃ無いですよ。
せめて少しくらい内容を説明するとかして欲しいなあ。
とりあえずここにいる人全部がこんな長月さんに対して黙って済ます訳は無い。
「おい長月、そんな言い方だと気になるだろ。せめてどんな案だったかくらいは言ってくれよ。」
「そうよ~。教えてくれないと今夜気になって眠れないと思うわ~。」
霜月さんと皐月さんが一緒になって迫る。けれど長月さんは無言のまま首を振るだけ。
あたしも気になるけど、細かい事を気にしてられないし。
という事であたしは手をパンパンと叩いた。
「はいはい、長月さんは喋りそうに無いから次行きましょう、次。他に何か案がある人。」
長月さんへ訊いていた人は納得がいかなかったみたいだったけど、しばらくして諦めたようだ。
そして手をすっと挙げた人が・・・。
「はいどうぞ、皐月さん。」
「は~い。あのね~、さくらを作ったらどうかしら~?」
「桜?あの、うちは駄菓子屋なんですけど。」
「違うわよ~、叩き売りでもして、そこへサクラの人が買いに来るの~。
そんでもって“これすっごく美味しい~”とかいって・・・。」
なんなのかしら、それ。サクラの人?うーん・・・。
考え込んでいると横から葉月さんが喋り出した。
「あのさあ、皐月さん。そんな販売をするほど寂れてるわけじゃないんだから。」
「けれどはぬけさん、これも一つの・・・」
「誰が歯抜けだい!?あたしは葉月!!」
いきなり葉月さんはがたっと立ちあがった。・・・びっくりしたあ。
「・・・はぐき?」
「は・づ・き!!!」
「は・・・んぐ。」
皐月さんが改めて言おうとしたところへ、その口を水無月さんが塞ぐ。
「もういいからあんたは黙ってなって。」
「んん~んん~。」
「葉月さんの言う通り、サクラなんてのは駄菓子屋でやるもんじゃないって。
それこそたたき売りなんてした日にゃ評判が悪くなっちまう。」
「んん~・・・。」
口を塞がれながらも暴れていた皐月さんだったけど、水無月さんの言葉を聞いてやがておとなしくなった。
葉月さんもどうやら落ち着いたようで、怒りを沈めてその場に座り直した。
やがて水無月さんも手を離し、皐月さんも黙ったままになる。
「ど、どうも水無月さん・・・。」
一応御礼は言っておこうかなって。そしたら・・・。
「いやいや。なかなかイカした説得方法だろ?」
「は、はあ・・・。」
どの辺がイカしたのかはさっぱり分からなかったけど、まあよしとしよう。
そろそろ終わりにした方がいいかな。もう出尽くしたかも。
見まわしてみると、それほど考え込んでいる人は居ないみたいだ。
というよりはさっきの皐月さんの言動に呆れているような・・・。
もしかして何か深い理由があるのかなあ?正しく人の名前を読んじゃいけないとか・・・。
今度調べてみよっかな。という前に師走さん辺りが言ってきそうだな・・・。
「・・・ちゃん、智子ちゃん。」
「はい?」
「どうすんの?意見はもう出尽くしたみたいだけど?」
「えっ?」
気がつくとみんながみんなあたしの方をじいーっと見ている。
なるほど、もうこれは終わった方が良さそうね。
「えー、皆さんの意見が全て出たようなので、この辺で終わりとします。
とりあえずまた明日、新製品の作り方等を検討したいと思うので、夜にここへ集まってください。」
『はーい。』
なんとなくつかれた感じのみなの返事。あたしも疲れてるけどね。
「それでは皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。」
『おやすみ。』
一度に挨拶したかと思うと、ざわざわとなりながらぞろぞろと出て行くみんな。
そこであたしは思いっきり伸びをした。とにかく疲れちゃったもんね・・・。
「智子ちゃん。」
「はい?あ、霧塚さん。なんですか?」
「ひとまず明日、早速作ってみるんですよね?」
「え、ええ。」
「色の材料は全て私が持ってきますから。つまり赤橙黄緑青藍紫ですわ。」
「虹の色ですね。お願いします。」
「ええ、それじゃあね、智子ちゃん。」
笑顔で会釈して霧塚さんは帰って行った。最後に残ったのは葉月さんのみ。
しばらくは座ったままボーっとしてたけど、やがて葉月さんが口を開く。
「やれやれ、疲れたねえ。」
「そうだねおばさん。でもあたしが頼んだものだし、弱音は吐いてられないよ。」
「ま、智子ちゃんがしっかりしてるならそれでいいさ。じゃあまた明日。」
「うん。おやすみなさーい。」
「ああ、おやすみ。」
挨拶を交わした後に、葉月さんは出ていった。
がらがらがらぴしゃん、という音がして、あたしは改めて机の上に突っ伏すのだった・・・。

そして翌日。早速昨日出た案になぞらって駄菓子を作ってみる事に。
できそうなのは霧塚さんの七色飴(なないろあめ)と菊月さんの複味菓子(ふくみがし)。
(レインボー飴ってのは意味的に違うんじゃないかってことで改名した)
水無月さんが言っていた折り紙のおまけは適当に任せる事にした。
とりあえず神無月さんは快く承知してくれたし。
で、いざ駄菓子を作ってみると・・・。
「菊月さん、なんだか変な味・・・。」
「うーん、やっぱり人工の味というのは良くないですね。ここまで難しいとは・・・。」
そう、複味菓子のできはいまいちなの。
人工の味と言っても、ほとんど天然素材なんだけどどうも上手くいかない。
部分部分で味が濃かったり薄かったり。更には味無しなんて部分も・・・。
「あたしは結構いい案だと思ったんだけどねえ・・・。」
「仕方が無いさ、現実は厳しいという事だ。菊月君、あきらめるかね?」
葉月さん、そして卯月さんが難しい顔をする。すると菊月さんも・・・。
「そうですね、私の考えが甘かった様です。これは無理があったんだ・・・。」
あっさり諦めちゃった。随分と早いなあ。もう少し粘るとかしないのかな・・・。
まあ、おとなしく中止するっていうもの一つの考えかな。
けれどあたしが思うに、これは作り方に問題があるんじゃ・・・。
「あの、菊月さん。どうして物ができあがってから味付けをするんですか?」
「できあがる途中に味付けをすると、完璧に混ざり合ってしまうんです。
そうなると、複数の味を楽しめるものじゃなくなる。」
「なるほど・・・。」
もっともだと思うんだけど、やっぱりあたしは・・・待てよ。
「ちょっと試したい事が出来たんで、これらの味の素材集借りますね。」
「え、ええどうぞ。」
一言断ると、あたしはもう一つのお菓子、七色飴を作っている場所へと向かった。
(つまりは別々に分担して作ってたって訳。当然作り方に関しては指導済み)
良く考えたら七色飴の味に関して深く考えてなかったんだ。
だからこの素材を使えば・・・。
そんなわけで現場に到着。そこには、懸命に作業する霧塚さんと師走さんが。
(今日はさすがに全員召集は無理だったので、極力来られる人だけになった)
「あら智子ちゃん、どうなさったんですか?」
「大体こっちの方は上手くいってるよ。ほら、ちゃんと七色に光る。」
チラッと師走さんが制作途中の飴を見せてくれた。おおっ、上出来上出来。
さっすが、パン屋さんと電気屋さん・・・って関係無いな。
こっちは素直に成功しそうで良かった。
「実は、この七色飴の味についてなんですけど。」
「味?」
「そうです。実は菊月さんの方はあんまり上手くいかなかったんです。
だから、その素材をこっちの味付けに使えないかなって。」
「なるほど、七色に光って七つの味を楽しめるわけですわね?」
ひらめいたの如くぽんと手を打った霧塚さん。
けれどそうじゃないんだな。菊月さんの言う通り、味が混ざっちゃうから。
「七つの味じゃなくって、ミックスした味です。」
「あら、そうなんですか。でもいい案ですわね。」
「それで、どんな味の素材を入れようというわけだい?」
そこで、適当に七つのフルーツの味の素材を取り出して並べる。
「色々組み合わせを試して行こうと思って。」
「なるほど。けど、色付けの段階でそれなりに味はそろってますから。」
「ま、思いつくままにやってみようぜ。それじゃあ早速!」
そんなわけで、少しずつ少しずつ。
これでもかといわんばかりに、慎重に慎重に。
三人ともが納得するような味をひねりにひねって作り出す。そして・・・。
「よし、これだ!!」
「ええ、これなら確かにおいしいですわね。万人うけしそうですし。」
「さてと、それじゃあ菊月さん達にも味見してもらってきますね。」
できあがった試作品一号をもって、菊月さん達が居る場所へ。
そして味見してもらうと、果たして合格点をくれた。
「うーん、これはおいしいといえますね。」
「ふむ、なかなかのものだ。他には無い独特の味だな。」
「やったじゃないか、智子ちゃん。これなら絶対大繁盛だよ!」
らしいといえばらしい誉め方。とにかくこれで七色飴は完成したも同然!
今度はこの七人で作業を進め、無事に商品としてできあがったのでした。

七色飴が店頭に並んで一週間。
水無月さんが作ったおまけはついてるわ、見た目も綺麗で味もいい。
というわけで飛ぶ様に売れてあっという間になくなった七色飴。
これは大成功!早速御礼をしなきゃ、と思ったんだけど・・・。
「ええっ!?もうあの色の素材は無いって!?」
「そうなんです。次にそれが入荷するのは一ヶ月も先の事。
何か他の代用品を使わないといけませんわ。」
「代用品ったって・・・。七色を出せる食べ物・・・って、何がありましたっけ?」
そう。とりあえず追加注文に答えるべく新たに作ろうとしたら、材料が足りない。
色付けってのが結構難しいみたいね。
更には、菊月さんの味の素材すらも在庫が怪しくなってきたもよう。
「なぜか最初にできたようなものが、今できないんです。
間違えてめもってしまったんですかねえ・・・。」
だって。ちょっと、今更それは無いって。どうやって追加を作れば・・・。
そんなわけで、今しばらくは材料入荷待ち状態。
材料さえそろえば、結構簡単に作ることが出来るのになあ・・・。
けれど、そんな事は関係無く水無月さんはおまけを届けてくれる。
「イカした折り紙だろう?“鉛筆削り”に“はえたたき”、そして“栓抜き”だ!」
「・・・どうも。」
何でこんな変なものばっかり・・・なんて文句は言っていられないのは分かってる。
正直言って、この水無月さんのおまけのおかげで、他の商品も結構売れてるし。
(結局は全ての商品におまけがついた。だってひっきりなしに持ってくるんだから余っちゃって)
とにかく、暇じゃなくなったってのがうれしいな。まだまだ駄菓子屋も捨てたもんじゃ無いってね。
それにしても御礼をどうしようかな。今回の件で関わった人全員にしないと・・・。
とは言ってもあたしができるのは・・・。
「智子ちゃーん!あ、いたいた。」
「居ますよ、店開いてるんですから。それで師走さん、なんの用ですか?」
「分かってるくせに、事件だよ事件。さ、早く来てくれ。」
「ちょ、ちょっと、店番はどうするんですか!?」
「大丈夫、悟君に頼んでおいた。内容は行きながら話す!」
「うえっ!?そんな勝手な~!!」
とまあ、これがやっぱり日常。探偵業で恩返し、かな。
でも、これぞ本末転倒ってやつかも・・・。
≪第五話終わり≫
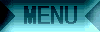 戻る
戻る